

『ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典』では、温暖化と高級魚、新高級魚と旧高級魚の話などなどを書いた。
書き加えたい話や、新しい情報も多々あるので、気がついたことを1年を通して書きとめる。
2025.5.10
本州から九州に普通に見られる標準和名(図鑑などに載るときの名)アイゴという魚は、見た目がとても地味だ。この標準和名は日本橋魚河岸で使われていた呼び名で、「あい」は棘のことで、「ご」には魚という意味がある。山菜に「あいこ(ミヤマイラクサ)」があるが、この「あい」も棘を表す。ともに棘だらけで刺されるとひどい目に遭う。本州の浅場の防波堤周りにもいる魚で子供でも釣り上げることができるのに、とても危険な魚である。
しかも、アイゴは食用魚としても地名度が低く、生まれて一度も見た事のない人も多いと思う。危険だし、見た目が地味なので一般的な認知度は極めて低い。高値で取り引きされているのは瀬戸内海の一部だけで、温かい海域でたくさん揚がるので比較的安く、国内だけではなく熱帯域でも愛されている大衆魚だ。
アイゴの仲間(スズキ目アイゴ科の魚)は世界的にみると30種もいるが、本州から九州にはアイゴ1種類しかいない。国内でも鹿児島県島嶼部、沖縄には15種以上のアイゴ科の魚がいる。熱帯に近づくほど姿も様々、大きさもまちまちのアイゴが存在する。本州から九州にいるアイゴは、もっとも北寄りに生息域を持つ変わり種だということに気づくだろう。
魚の値段には一定の法則がある。大きい種ほど高いのだ。本州などでアイゴを見ていると、このあまり大きくならない地味な魚の仲間に高級魚がいるの? と思われるかも知れないが、いるのである。
沖縄で主に食べられているゴマアイゴである。アイゴの仲間である証拠に胸鰭・尾鰭以外の鰭に鋭くて強い棘がある。沖縄県では「かーえー」と呼ばれている。
アイゴは小さいので網漁でとるが、ゴマアイゴは大きいので刺突漁(銛でついてとる)でとる。網漁は不特定多数の魚をとるために、別に値段が高くなくてもとりあえずとるわけで、中にはミズンとか「ぐるくん(タカサゴ)」のように加工品などにも使われる、安い魚もいる。
銛で突いてとるのは原則的に高級魚だけである。「あかじんみーばい(スジアラ)」、「ちんすーあかじん(コクハンアラ)」や「げんなー(ナンヨウブダイ)」、「まくぶ(シロクラベラ)」などをとっているが、そこにアイゴ科のゴマアイゴが含まれるのだ。
ゴマアイゴは、とにかく見た目で圧倒されるはずだ。アイゴと比べると体高がある上に、全長50cm以上になる。国内で揚がるアイゴの仲間の最大種でもある。
非常に美しい魚で、全身に黄金色の斑紋が散らばり、尾鰭の前にも黄金色の大きな斑紋がある。英語でゴールデンラビットフィッシュ。ラビットフィッシュ(ウサギのような顔をした魚)はアイゴの英名で、金色の斑紋がとてもきれいなので、ゴールデンなのだ。
ダイビングで沖縄に行った女性が「(海の中で)『かーえー』を見て感激して、料理店で刺身を食べておいしかった」などと大騒ぎをしているのを見たことがあるが、そんな魚でもある。
釣りの世界でも人気がある。あまり大きくならないアイゴは子供連れが狙うものだが、本種は船や磯から本格的な仕掛けで釣る人気のターゲットである。大型が釣れると魚拓をとって釣具店に飾られたりする。
さて、繰り返しになるが、今回の沖縄で高値をつけるゴマアイゴは奄美大島以南に多く、食用魚としても重要である。台湾や西太平洋の熱帯域に広い生息域を持っていて、この熱帯域でも人気がある。
アイゴが安いのは、往々にして臭味があるからだが、本種に臭味はない。扱いが悪いと臭味が出るものの、これは魚としては普通である。
沖縄で、刺身で出てくると、これがアイゴの仲間だとは思わないだろう。血合いが赤く、身に透明感がある。沖縄の魚の特徴で、脂ののりはそこそこといったところだが、味がある。うま味豊かで、身に甘味がある。食べ続けても飽きが来ない。よくよく噛みしめると微かに臭みがあるが、実はこれも味なのである。
年間を通しておいしいけれど、沖縄のむーちー(旧暦の12月8日で植物の月桃で巻いた餅を振る舞う時季)の2月1日前後から4月くらいまでは脂がのっている。
沖縄の魚はみな北上傾向にある。「あかじんみーばい(スジアラ)」は沖縄きっての超高級魚であるが、今や本州でも見られる。ところが本種はなかなか北上しない。
今のところ、奄美大島以南の魚だが、先物買いというか、本種の味を知っておくのも悪くないと思う。
 「ゴマアイゴの刺身」
「ゴマアイゴの刺身」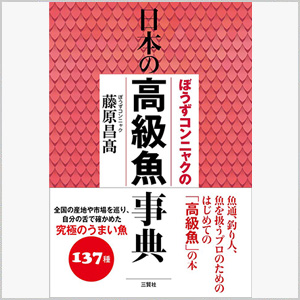
徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)生まれ。ウェブサイト「ぼうずコンニャクの市場魚貝類図鑑」主宰、40余年にわたり日本全国で収集した魚貝類の情報を公開し、ページビューは月間200万にのぼる。『ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典』(三賢社)、『からだにおいしい魚の便利帳』(高橋書店)、『すし図鑑』『美味しいマイナー魚介図鑑』(ともにマイナビ出版)など著書も多数。