

『ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典』では、温暖化と高級魚、新高級魚と旧高級魚の話などなどを書いた。
書き加えたい話や、新しい情報も多々あるので、気がついたことを1年を通して書きとめる。
2025.5.26
1945年、敗戦の年から現在に至るまで、価値観がもっとも変わった魚が「目抜け」と呼ばれる赤い大型魚である。昔は安い魚の代名詞、今や市場で買うと、拍手されるほど高嶺の花である。
流通上の「目抜け」と呼ばれる魚について書いておく必要があるだろう。スズキ目カサゴ亜目メバル科メバル属(分類もおぼえておくと便利)の魚で、銚子以北に(少ないながら相模湾にも)いる赤い大型の深海魚だ。標準和名はオオサガ、ヒレグロメヌケ、バラメヌケ、アラメヌケ。深海から釣り上げられるとき、水圧のために目の皮膜、眼球が飛び出す。目が抜けるので「目抜け」である。
余談だが、もっと大きな括りに「赤魚」というのがあり、ここにはキチジ(きんき)や、アラスカメヌケ(赤魚)、が含まれるようになるというのもおぼえておいて損はない。
国内の水産流通の歴史の中で、「目抜け」ほど悪名高い魚もいなかった。1960年代以前に現役の料理人だった方達は、この赤い深海魚を今でも忌み嫌っていて、その扱いにくさ、人気のなさを語る。この時代、脂の少ない上品な味の魚が高く、脂の多い「目抜け」は嫌われて安かったのである。北洋や北海道で水揚げされて、消費地に持ってくるのに時間がかかり鮮度がよくなかったのもある。
ところがこの国の人の嗜好が劇的に変化し、脂を好むようになって「目抜け」人気が急上昇する。流通の発達から鮮度がよくなったのもあるだろう。
「目抜け」は主に東北地方太平洋側、北海道太平洋側・オホーツク海、北洋で水揚げされる。これに対して千葉県以南の太平洋側で揚がる、大型のまったく同様の深海魚がアコウダイ、ホウズキである。
この「目抜け」5種の中でもっとも高いのはオオサガだ。1キロ1万円ということも珍しくない。ついでヒレグロメヌケ。バラメヌケ、アラメヌケはやや小型なので安いものの、この赤い大型のメバル類(メバル科メバル属)はすべて高級魚である。
昔はこの「目抜け」を漬け魚(みそ漬け・粕漬け)にしていた。安くておいしいと評判だったという。今、国産の「目抜け」でみそ漬けなどを作ると1切れ4000円で買えるかどうか。
先にも述べたように「目抜け」でいちばん値が高いのがオオサガである。重さ10キロ以上になる大型魚で、市場では「本目抜け」と呼ばれている。また「こうじんめぬけ(荒神目抜け)」という荒々しい呼び名もある。
このオオサガが今や幻の魚となっている。希に水揚げがあるものの、豊洲などでは途方もなく高価で、商材としての魅力をなくしている。
頂点にいた、「本目抜け」に代わって登場するのが、もっと北にいるヒレグロメヌケだ。これが「目抜け」の主役になりつつあるのである。北海道太平洋側以南にはほとんどいない魚で、今現在、市場で見られるのは、ほぼ総て北海道羅臼産だ。
いかにオオサガが「本目抜け」として人気があっても、不漁が続くと、市場での認知度が下がる。これと呼応するようにヒレグロメヌケの入荷量が増える。いつの間にか「目抜け」といえば羅臼、という認識が生まれている。北海道から航空便でやってくるので、鮮度がいいことも本種が注目を浴びるきっかけになった。
ヒレグロメヌケは国内では岩手県以北、オホーツク海からアラスカ湾、北アメリカのカリフォルニア州に生息している。名前通りに鰭の縁が黒く、オオサガ以上に大きくなり、体長1メートルを超え、重さ20キロ以上にもなる。
北の海の赤い深海魚の身質には共通点がある。普通は筋繊維の間や皮下に脂があるのに対して、こちらは薄い筋繊維に脂が包まれているのである。体に脂が充満していて、とても柔らかい。その体を海中で支えているのが浮力のある脂と考えてもいい。だから市場などで触るとびっくりするくらい柔らかい。
この筋肉と脂の関係はキチジ(きんき)と同じである。キチジも昔は蒲鉾になっていた時代があるが、今や高級魚の代名詞となっている。これと同じ性質の身質を持つ「目抜け」の高騰は当たり前のことなのだ。
ヒレグロメヌケも焼くとキチジ同様、中から大量の脂が吹き出してくる。身が脂に包まれてときどき炎があがる。焼くと表面が香ばしく、中が脂で満たされる。
それ以上に本種の評価を上げたのは生食である。身にはうま味もあるものの、むしろ脂の口溶け感からくる甘味の方が先に来る。普通、皮を生かして焼霜造りにする。身よりも皮にうま味があるからである。
さて、オオサガが減ったのはとりすぎである可能性が高い。水揚げされる平均的な重さである4キロ以上になるのに10年以上かかる。これはヒレグロメヌケにも当てはまるので、資源に関しては不安が残る。
ちなみに主に東京湾口以南にいるアコウダイが減少して、その穴を埋めた形なのが、北の「目抜け」である。この「目抜け」でもっともたくさん揚がって味がよかったのがオオサガ、それが今やオホーツク海のヒレグロメヌケに主役の座を明け渡している。ヒレグロメヌケの次は国内海域にいるのだろうか。
 「ヒレグロメヌケの焼霜造り」
「ヒレグロメヌケの焼霜造り」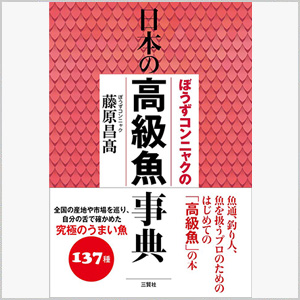
徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)生まれ。ウェブサイト「ぼうずコンニャクの市場魚貝類図鑑」主宰、40余年にわたり日本全国で収集した魚貝類の情報を公開し、ページビューは月間200万にのぼる。『ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典』(三賢社)、『からだにおいしい魚の便利帳』(高橋書店)、『すし図鑑』『美味しいマイナー魚介図鑑』(ともにマイナビ出版)など著書も多数。